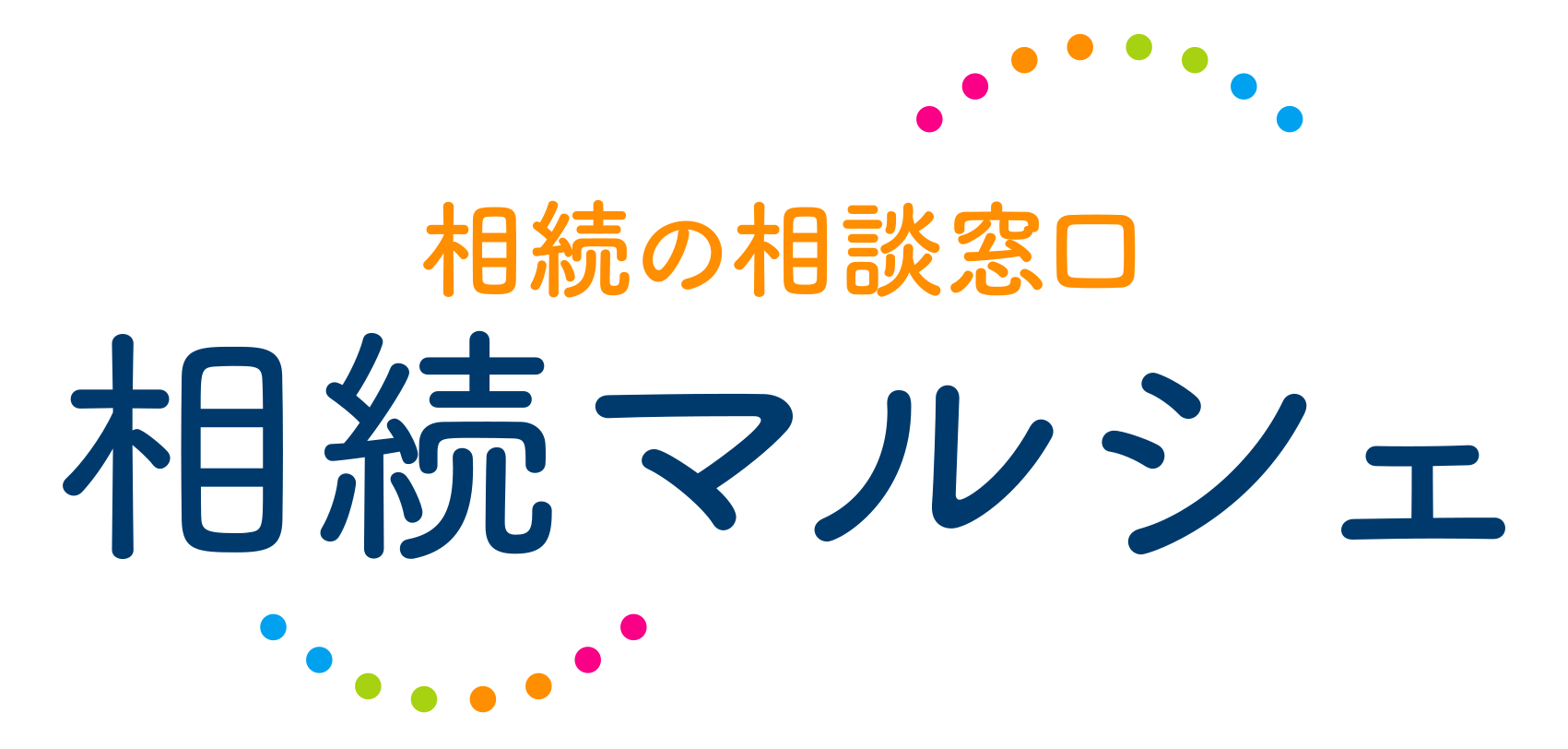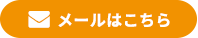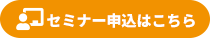ブログ
認知症と相続|遺言・成年後見・家族信託で備える対策を解説
更新日:2025.10.27 コラム
高齢化社会が進み、認知症の方が増加しています。それに伴って相続に関する悩みを抱える方も増えています。
認知症になると、法律上「意思能力がない」と判断され、遺言書の作成や財産の処分ができなくなる可能性があります。しかし、適切な準備と対策を講じることで、本人の意思を尊重しながら円滑な財産管理や相続を実現することができます。
この記事では、認知症と相続にまつわる法律問題から、成年後見制度、家族信託などの具体的な対策まで解説します。
認知症になると遺言書が無効になる可能性
意思能力が必要な理由
遺言書を作成するには、「遺言能力」つまり遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力が必要です。認知症が進行すると、この能力が失われたと判断される場合があります。
遺言能力が問われるケース
- 認知症の診断を受けている
- 要介護認定を受けている
- 介護施設に入所している
- 日常生活に支障が出ている
無効になる具体例
ケース1:重度の認知症の場合 医師から「認知症により判断能力が著しく低下している」と診断されている状態で作成された遺言書は、後に相続人から無効を主張される可能性が高くなります。
ケース2:意思能力の証明が困難 遺言書作成時の医療記録、診断書、介護記録などから、本人に判断能力がなかったことが証明されると、遺言が無効と判断されることがあります。
有効な遺言を残すためのポイント
公正証書遺言の作成 公証人が本人の意思能力を確認するため、後の紛争リスクを低減できます。
医師の診断書を取得 遺言書作成時に、精神科医や主治医による「遺言能力がある」旨の診断書を取得しておくと、有効性の証明に役立ちます。
ビデオ撮影の活用 本人が遺言の内容を理解し、自らの意思で作成していることを記録しておくことも有効です。
成年後見制度の仕組みと活用
成年後見制度とは
認知症などで判断能力が不十分になった方を保護・支援するための制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産管理や契約行為を代理します。
成年後見制度の種類
- 後見:判断能力がほぼない場合
- 保佐:判断能力が著しく不十分な場合
- 補助:判断能力が不十分な場合
成年後見人ができること
財産管理
- 預貯金の管理・引き出し
- 不動産の管理(売却には家庭裁判所の許可が必要)
- 年金の受け取り
- 税金・公共料金の支払い
身上監護
- 介護施設への入所契約
- 医療契約
- 住居の確保
成年後見制度の注意点
できないこと
- 遺言書の作成を代理すること
- 本人の死後の相続手続き
- 投資など積極的な資産運用
デメリット
- 後見人への報酬が必要(月額2〜6万円程度)
- 家庭裁判所への定期報告義務
- 本人が亡くなるまで続く
- 柔軟な財産活用ができない
家族信託による財産管理
家族信託とは
認知症になる前に、信頼できる家族に財産の管理・処分を託す仕組みです。成年後見制度と異なり、柔軟な財産管理が可能です。
家族信託の基本構造
- 委託者:財産を託す人(親)
- 受託者:財産を管理する人(子など)
- 受益者:利益を受ける人(通常は委託者本人)
家族信託のメリット
柔軟な財産管理
- 不動産の売却・賃貸管理
- 積極的な資産運用
- 贈与や相続対策の実行
認知症対策として優れている点
- 委託者が認知症になっても信託契約は継続
- 受託者が引き続き財産を管理できる
- 家庭裁判所の関与が不要
具体的な活用例
例1:賃貸不動産の管理 父親が所有するアパートを子に信託。父が認知症になっても、子が賃貸経営を継続し、父の生活費に充てることができます。
例2:実家の売却 実家を子に信託。父が老人ホームに入居する際、子が実家を売却し、その資金を入居費用に充てることができます。
家族信託の注意点
設定時のコスト
- 公正証書作成費用:数万円
- 登記費用:不動産価格の0.3〜0.4%
- 専門家報酬:30〜100万円程度
受託者の責任 受託者は財産を適切に管理する法的責任を負います。不適切な管理は損害賠償責任につながる可能性があります。
生前贈与でできること・できないこと
認知症になる前の生前贈与
できること
- 年110万円までの暦年贈与(贈与税非課税)
- 相続時精算課税制度の利用
- 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与
メリット
- 相続財産を減らし、相続税対策になる
- 生前に財産を分けることで、相続争いを防げる
- 贈与者が財産の使われ方を見届けられる
認知症になった後の制約
原則としてできないこと 認知症により判断能力がなくなると、本人が贈与契約を結ぶことはできません。
成年後見人による贈与の制限 成年後見人は原則として贈与を行えません。ただし、以下の場合は例外的に認められることがあります
例外的に認められる場合
- 扶養義務の範囲内(生活費、教育費)
- 社会通念上相当な範囲の贈与(お年玉、お祝い金など)
- 家庭裁判所の許可を得た特別な事情がある場合
相続人に認知症の人がいる場合の対応
遺産分割協議ができない問題
相続が発生した際、相続人の中に認知症の方がいる場合、大きな問題が生じます。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですが、判断能力がない方は法律上、協議に参加できないためです。
起こる問題
- 遺産分割協議が進められない
- 不動産の名義変更ができない
- 預貯金の解約・分配ができない
- 相続税の申告に支障が出る可能性
成年後見人の選任が必要
認知症の相続人が遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。
手続きの流れ
- 家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て
- 医師による鑑定(必要に応じて)
- 後見人の選任
- 後見人が本人を代理して遺産分割協議に参加
選任にかかる期間 通常、申立てから選任まで2〜4ヶ月程度かかります。相続税の申告期限(10ヶ月)を考慮すると、早めの対応が重要です。
特別代理人が必要なケース
後見人と被後見人が両方とも相続人である場合、「利益相反」となるため、後見人は被後見人を代理できません。この場合、特別代理人の選任が必要です。
具体例 母が亡くなり、父(認知症)と長男が相続人の場合
- 長男が父の後見人である
- 長男と父の両方が相続人
- 長男が父を代理すると、自分の取り分を増やすこともできてしまう
- →特別代理人の選任が必要
特別代理人の選任手続き
- 家庭裁判所に特別代理人選任の申立て
- 遺産分割協議案の提出
- 特別代理人の選任(通常1〜2ヶ月)
- 特別代理人が認知症の相続人を代理して協議
成年後見人による遺産分割の注意点
成年後見人は、本人の利益を最優先に考えなければなりません。そのため、以下のような制約があります
原則
- 法定相続分以上の取得を目指す
- 不利な内容の遺産分割には合意できない
- 本人の取り分をゼロにすることはできない
例外的に認められる場合
- 本人が居住用不動産を取得し、他の相続人が代償金を支払う
- 換価分割で全員が公平に現金を受け取る
- 家庭裁判所の許可を得た合理的な理由がある場合
まとめ
認知症にまつわる相続の問題は、「いつか対策しよう」と先延ばしにしているうちに、手遅れになってしまうケースが非常に多いです。認知症が進行してからでは、遺言書の作成も家族信託の設定もできなくなり、選択肢が大幅に限られてしまいます。
親が元気なうちは「まだ早い」と感じるかもしれませんが、認知症はいつ発症するかわかりません。家族で話し合い、専門家に相談しながら、早めに対策を進めることが、本人の意思を尊重し、家族の負担を軽減する最善の方法です。
相続マルシェでは、税理士・弁護士・司法書士と提携し、お客様の状況に応じた最適なご提案をいたします。事前のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら↓