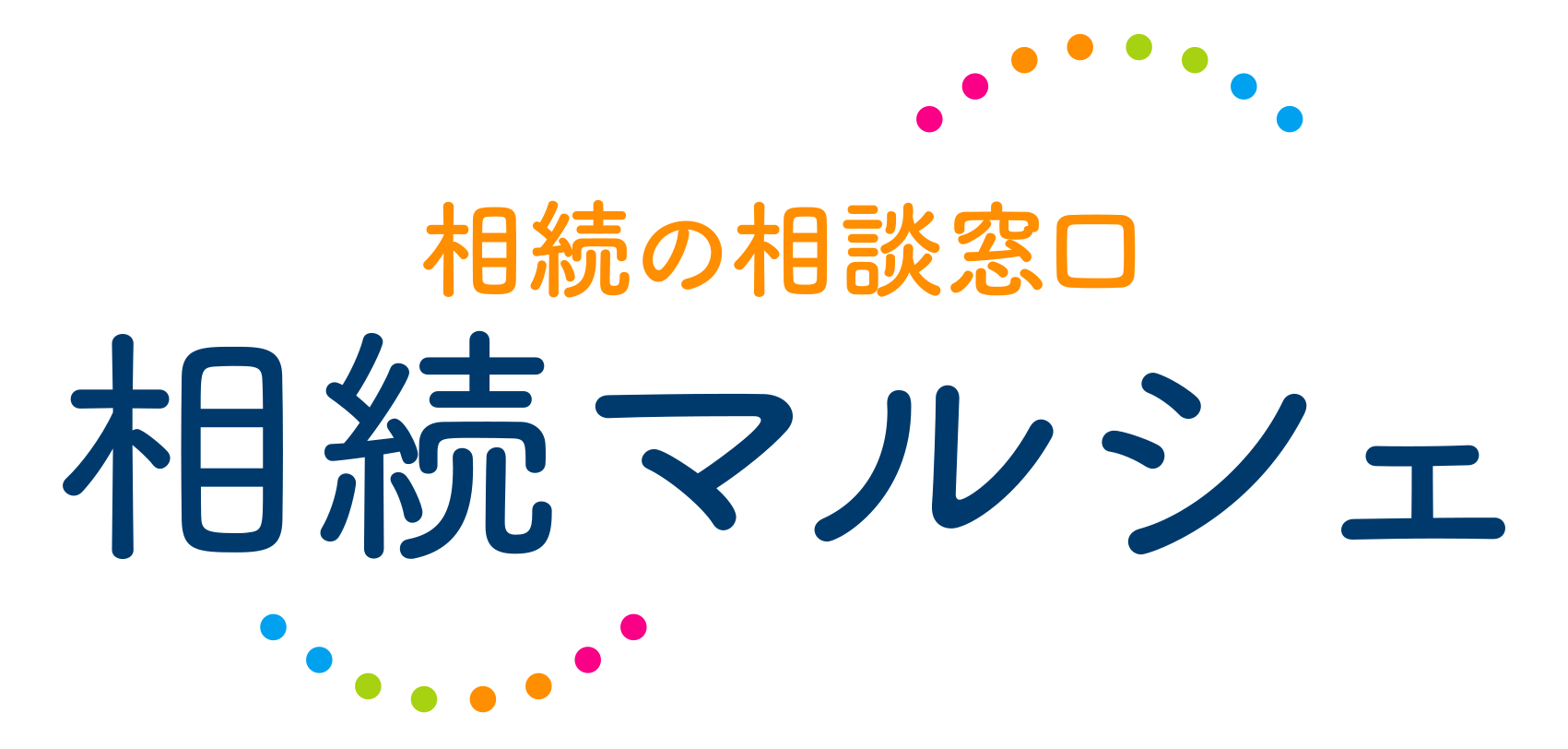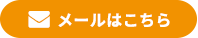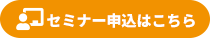ブログ
相続税とは?仕組み・計算方法・節税ポイントをわかりやすく解説
更新日:2025.09.30 コラム
「親が亡くなったら相続税はかかるのだろうか?」「そもそも相続税ってどんな仕組みなの?」相続が発生した際、多くの方がこのような疑問を抱きます。相続税とは、亡くなった方から財産を受け継ぐ際に課される国税ですが、すべての相続に課税されるわけではありません。
相続税は複雑な制度に思えますが、基本的な仕組みを理解すれば、自分のケースが課税対象になるか、どのような対策が必要かが見えてきます。この記事では、相続税の基礎知識から計算方法、節税対策まで、わかりやすく解説します。
相続税とは?
相続税の基本的な仕組み
相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に課される税金です。この税金は、財産を受け取った人(相続人や受遺者)が負担することになります。
相続税は一定額以上の財産を相続した場合にのみ課税されます。つまり、少額の相続であれば相続税はかからず、多くの方が心配するほど身近な税金ではありません。
しかし、不動産を所有している場合や、一定の財産がある場合には、課税対象となる可能性があるため、基本的な仕組みを理解しておくことが重要です。
どんな財産が課税対象になるのか
課税対象となる財産は、被相続人が所有していたほぼすべての経済的価値のあるものです
プラスの財産
現金、預貯金、有価証券(株式、債券など)、不動産(土地、建物)、事業用資産、貴金属、骨董品、自動車などが含まれます。また、生命保険金や死亡退職金も一定額を超える部分は課税対象となります。
マイナスの財産
借金や未払いの税金なども相続の対象となり、相続税の計算では財産から差し引くことができます。
みなし相続財産
生命保険金や死亡退職金など、被相続人の死亡により取得する財産も、一定の非課税枠を超える部分は相続税の対象となります。
相続税がかかる条件
相続税の課税対象者
相続税がかかるかどうかは、相続財産の合計額が基礎控除額を超えるかどうかで決まります。基礎控除額以下の場合は相続税はかからず、申告も不要です。
課税対象となるのは、日本国内に住所がある人が相続人である場合、または海外に住んでいても日本国籍を持つ人が相続人である場合などです。
課税される財産の範囲
相続税の計算では、以下の手順で課税価格を算出します
計算の基本的な流れ
- 被相続人の全財産の評価額を算出
- 債務や葬式費用を差し引く
- 相続開始前7年以内の暦年課税の贈与や過去に相続時精算課税制度を利用していればその利用分を加算
- 基礎控除額と比較して課税の有無を判定
この計算により、相続税がかかるかどうかが決まります。
相続税の計算方法と基礎控除
基礎控除額の計算式
基礎控除は以下の計算式で求められます
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
具体例
- 配偶者と子2人が相続人の場合:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
- 配偶者と子1人が相続人の場合:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
- 配偶者のみが相続人の場合:3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円
この基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
税率の仕組み
基礎控除額を超えた部分に対して累進税率が適用されます。
各相続人の取得金額に応じて以下の税率が適用されます
- 1,000万円以下:10%
- 3,000万円以下:15%(控除額50万円)
- 5,000万円以下:20%(控除額200万円)
- 1億円以下:30%(控除額700万円)
- 2億円以下:40%(控除額1,700万円)
- 3億円以下:45%(控除額2,700万円)
- 6億円以下:50%(控除額4,200万円)
- 6億円超:55%(控除額7,200万円)
実際の計算例
相続財産6,000万円、相続人が配偶者と子1人(法定相続分1/2ずつ)の場合
- 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
- 課税遺産総額:6,000万円 – 4,200万円 = 1,800万円
- 各人の法定相続分:1,800万円 × 1/2 = 900万円ずつ
- 相続税額:900万円 × 10% = 90万円ずつ
- 相続税総額:90万円 × 2人 = 180万円
ただし、配偶者には配偶者控除があるため、実際の税額はさらに軽減されます。
相続税の申告・納付について
申告が必要なケース
相続税の申告が必要なのは、相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合です。ただし、以下の特例を利用する場合は、結果的に税額がゼロになっても申告が必要です。
- 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
- 小規模宅地等の特例
- 農地の納税猶予の特例
これらの特例により相続税がかからなくなる場合でも、申告書の提出は必須となります。
期限
相続税申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。この期限は非常に重要で、遅れると加算税や延滞税が課される可能性があります。
- 3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の期限
- 4ヶ月以内:準確定申告の期限(被相続人の所得税)
- 10ヶ月以内:相続税の申告・納付期限
申告に必要な書類と流れ
相続税の申告には多くの書類が必要です。
基本書類
- 相続税申告書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(または遺言書)
財産関係書類
- 不動産:登記事項証明書、固定資産税評価証明書
- 預貯金:残高証明書、取引明細書
- 有価証券:評価証明書
- 生命保険:保険証券、支払通知書
申告書の作成は複雑なため、多くの場合、税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。
相続税の節税対策
生前贈与
相続税節税対策として最も簡単に行えるのが、生前贈与です。ただし、そのやり方によっては、税金が余計にかかるなど、不利益が大きくなる可能性もありますので注意が必要です。
暦年贈与 年間110万円までの基礎控除を活用し、長期間にわたって財産を移転する方法です。早い時期から計画的に行うことで、確実な節税効果が期待できます。
相続時精算課税制度 2,500万円まで贈与税なしで贈与でき、相続時に贈与財産を相続財産に加算して計算する制度です。値上がりが期待される財産に有効です。また、近年では暦年課税との併用も認められ(ただし、注意点あり)、利用しやすい制度になりつつあります。
小規模宅地等の特例
被相続人の居住用や事業用の宅地について、一定の条件を満たす場合に大幅な評価減を受けられる制度です。
- 居住用宅地:330㎡まで80%の評価減
- 事業用宅地:400㎡まで80%の評価減
- 貸付事業用宅地:200㎡まで50%の評価減
この特例により、数千万円の節税効果を得られる場合があります。
配偶者控除
配偶者は以下のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
ただし、二次相続(配偶者が亡くなった時の相続)も考慮した総合的な判断が重要です。
遺言の活用
適切な遺言書の作成により、以下の効果が期待できます。
- 各種特例の適用を確実にする
- 相続人間の争いを防ぎ、円滑な申告を可能にする
- 二次相続も考慮した最適な財産分割を実現する
申告漏れのペナルティ
相続税の申告漏れや期限の遅れには重いペナルティが課されます。
加算税
- 過少申告加算税:追加税額の10%~15%
- 無申告加算税:税額の15%~20%
- 重加算税:税額の35%~40%(悪質な場合)
延滞税 申告期限または法定納期限から実際の納付日まで年7.3%~14.6%の延滞税が課されます。
まとめ
相続税とは、一定額以上の財産を相続した場合に課される税金ですが、基礎控除や各種特例により、多くのケースで税負担を軽減できます。重要なのは、制度を正しく理解し、適切な対策を講じることです。
重要なポイント
- 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に課税
- 申告期限は相続開始から10ヶ月以内
- 生前贈与、小規模宅地等の特例、配偶者控除などの節税対策が有効
- 専門家による総合的なサポートが重要
相続税は誰にでも起こり得る問題ですが、早めの準備と適切な対策により、税負担を大幅に軽減することが可能です。不安を感じたら、まずは専門家に相談して、あなたの状況に最適な対策を検討することをお勧めします。
適切な知識と準備により、安心して相続を迎えることができるようになります。
相続マルシェでは、税理士・弁護士・司法書士と提携し、お客様の状況に応じた最適なご提案をいたします。事前のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら↓