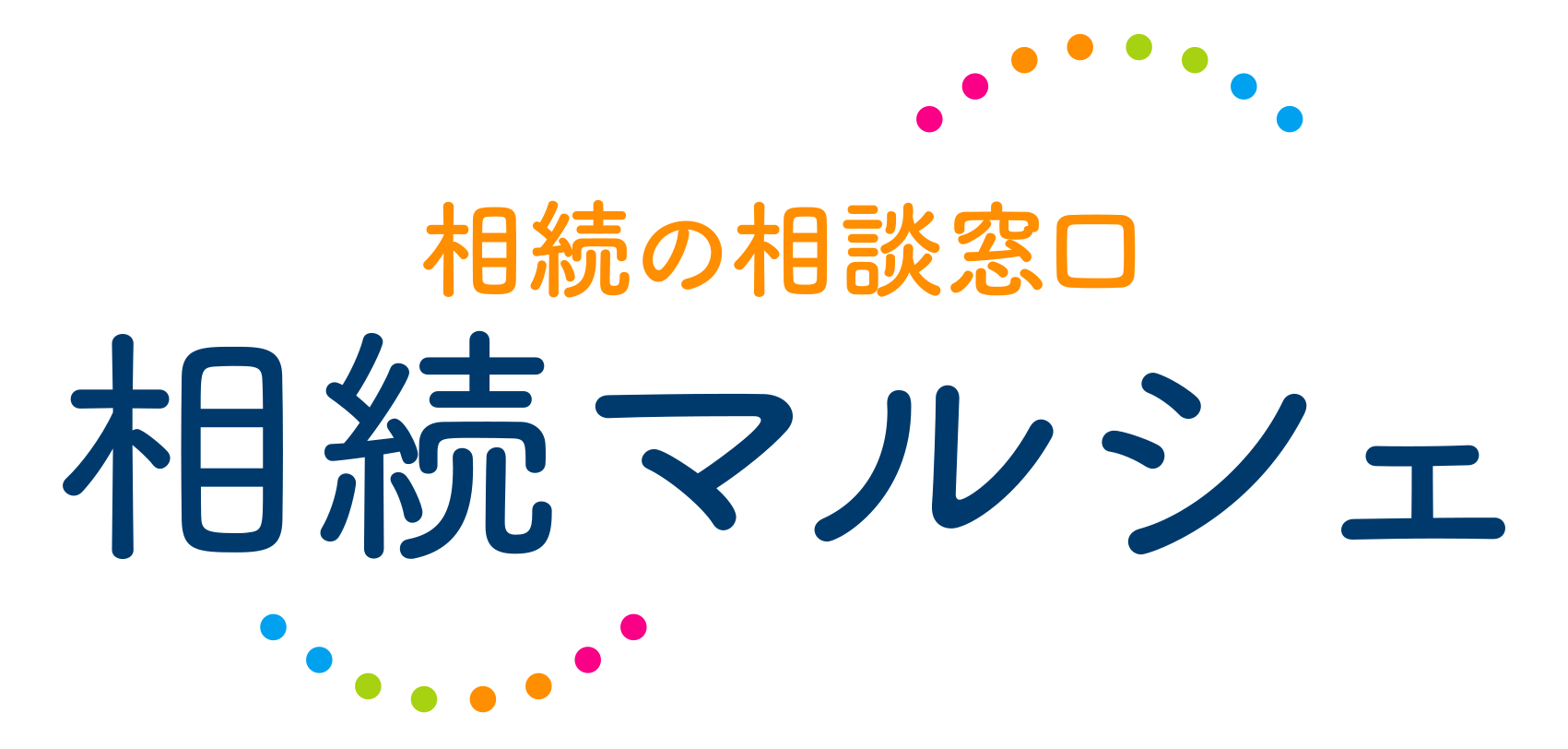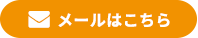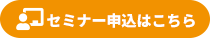ブログ
家族信託(民事信託)とは?認知症対策と相続対策の新しい選択肢
更新日:2025.11.28 コラム
「もし自分が認知症になったら、財産の管理はどうなるのだろう」「成年後見制度は手続きが大変そう」「元気なうちに、財産管理を子どもに任せられないだろうか」――このような不安や疑問を持つ方が増えています。
そんな中、近年注目を集めているのが「家族信託(民事信託)」という仕組みです。認知症対策や相続対策として、柔軟で使いやすい制度として広まりつつあります。従来の成年後見制度や遺言とは異なるアプローチで、財産管理と承継の問題を解決できる可能性があります。
この記事では、家族信託とは何か、なぜ注目されているのか、どんな場面で活用できるのか、そして注意すべき点について、解説します。
家族信託(民事信託)とは?
家族信託とは、簡単に言えば「信頼できる家族に、自分の財産の管理を任せる」仕組みです。信託法という法律に基づく制度で、正式には「民事信託」と呼ばれますが、家族間で行うことが多いため「家族信託」という呼び方が一般的になっています。
委託者・受託者・受益者の関係
家族信託には、3つの立場の人が登場します。
- 委託者(いたくしゃ):財産を持っていて、管理を任せる人(例:父親本人)
- 受託者(じゅたくしゃ):財産を預かり、管理・運用する人(例:長男)
- 受益者(じゅえきしゃ):財産から生まれる利益を受け取る人(例:父親本人)
例えば、父親(委託者)が自分の不動産や預金を長男(受託者)に信託し、その財産から得られる家賃収入などを父親自身(受益者)が受け取る、という形が典型的です。委託者と受益者が同じ人というケースが多くあります。
受託者は、あくまで「管理する人」であり、財産の所有者は受益者です。受託者が勝手に財産を使ったり売却したりすることはできず、信託契約で定めた目的の範囲内でのみ管理・運用を行います。
相続や遺言との違い
遺言は、亡くなった後の財産の分け方を指定するものです。一方、家族信託は、生きている間の財産管理と、亡くなった後の承継の両方をカバーできます。
相続は、亡くなった後に財産を引き継ぐタイミングが決まっていますが、家族信託は元気なうちに契約を結び、将来に備えることができます。また、「父→長男→孫」というように、複数世代にわたる承継の指定もできるという特徴があります(遺言では次の世代までしか指定できません)。
成年後見制度とも違い、成年後見制度は判断能力が低下してから家庭裁判所に申し立てて開始しますが、家族信託は元気なうちに契約を結び、将来に備えます。また、成年後見制度では財産の処分や運用には家庭裁判所の許可が必要で、柔軟な運用がしにくいという特徴がありますが、家族信託では契約内容次第で柔軟な対応が可能です。
家族信託が注目される理由
認知症対策として有効
日本は超高齢社会を迎え、認知症の方も増加しています。認知症で判断能力が低下すると、本人名義の預金口座が凍結され、不動産の売却や管理契約もできなくなります。これは本人だけでなく、家族にとっても大きな負担です。
家族信託を設定しておけば、委託者が認知症になっても、受託者が引き続き財産を管理できます。賃貸アパートの修繕契約、株式の売買、預金の引き出しなど、必要な対応を止めることなく続けられるのです。
成年後見制度も認知症対策の一つですが、家庭裁判所への申立て、後見人の選任、年次報告の義務など、手続きが煩雑です。また、後見人が家族以外の専門職(弁護士や司法書士)になることもあり、報酬が継続的に発生します。家族信託なら、基本的に家族のみで進められ、より柔軟に財産管理を行える点がメリットです。
相続開始前から財産を柔軟に管理できる
従来の相続対策は、「亡くなった後」にどう財産を分けるかに焦点が当てられていました。しかし、家族信託は「生きている間」の財産管理もカバーできます。
例えば、高齢の親が元気なうちは自分で管理し、判断能力が低下したら子どもが代わりに管理、そして親が亡くなった後は事前に決めた通りに承継される、という一連の流れを一つの契約でカバーできるのです。
また、契約内容を柔軟に設計できるため、「不動産は売却してもいい」「株式は保有し続ける」など、財産ごとに異なる管理方法を指定することも可能です。家族の状況に合わせた細かな対応ができる点が、大きな魅力といえます。
活用される主なケース
家族信託は、具体的にどのような場面で活用されているのでしょうか。代表的なケースを見てみましょう。
【ケース1:高齢の親の資産を子が管理】
70代のAさんは、まだ元気ですが、将来認知症になったときのことが心配です。賃貸アパートを持っているため、判断能力が低下すると、修繕の契約や入居者対応ができなくなる可能性があります。
そこで、Aさんは長女と家族信託契約を結び、アパートの管理を任せることにしました。Aさんが認知症になっても、長女の判断で必要な修繕や管理ができるため、アパート経営を続けられます。賃料収入はAさんが受け取り、生活費や介護費用に充てることができます。
このように、高齢の親の財産を子どもが管理することで、認知症になっても財産が凍結されず、スムーズに生活や事業を続けられます。
【ケース2:不動産や預金をスムーズに承継したい場合】
Bさんは、自宅と収益不動産を持っています。自宅は長男に、収益不動産は次男に継がせたいと考えていますが、遺言だけでは自分が認知症になったときの対応ができません。
家族信託を使えば、Bさんが元気なうちは自分で管理し、判断能力が低下したら長男が代わりに管理、そしてBさんが亡くなった後は、自宅は長男へ、収益不動産は次男へ、という承継の流れを一つの契約で実現できます。
さらに、「長男が亡くなったら孫へ」というように、次の次の世代まで承継先を決めておくこともできます。これは遺言ではできない、家族信託ならではのメリットです。
【ケース3:障がいのある子どもの将来を守りたい】
Cさんには知的障がいのある次男がいます。Cさんが亡くなった後、次男が一人で財産管理できるか心配です。
そこで、長男を受託者、次男を受益者とする家族信託を設定しました。Cさんの財産は長男が管理し、次男の生活に必要な資金を定期的に支払う仕組みです。次男の生活を長期的に守ることができます。
このように、家族信託は様々な家族の事情に対応できる柔軟な制度なのです。
家族信託の注意点・デメリット
信託契約の作成に専門知識が必要
家族信託は自由度が高い分、契約内容をどう設計するかが非常に重要です。法律的に有効で、あなたの意図が正確に反映された契約書を作成するには、専門家のサポートが不可欠です。
弁護士や司法書士など、家族信託に詳しい専門家に相談しながら、慎重に内容を決める必要があります。契約書の作成費用や、不動産の信託登記費用など、初期費用がかかることも認識しておきましょう。一般的には、30万円〜100万円程度の費用が必要になることが多いです。
登記や税金の扱いに注意
不動産を信託する場合、法務局で「信託登記」を行う必要があります。登記費用(登録免許税)がかかるため、事前に確認しておきましょう。
税金については、受益者が利益を受け取る時点で課税されます。委託者と受益者が同じ場合(自益信託)は、通常、信託設定時に贈与税はかかりません。しかし、受益者が変更される場合(他益信託)には、贈与税や相続税が発生する可能性があります。税務上の扱いは複雑なため、税理士への相談も必要です。
信頼できる受託者が必要
家族信託では、受託者に大きな権限が与えられます。そのため、誠実で責任感のある家族を受託者に選ぶことが最も重要です。信頼関係がなければ、制度はうまく機能しません。
また、一部の子どもだけが受託者になる場合、他の家族が不公平に感じる可能性もあります。事前に家族で話し合い、理解を得ることが大切です。
すべての財産を信託できるわけではない
年金や生活保護などの社会保障給付は信託できません。また、金融機関によっては信託口座の開設に対応していないこともあります。すべての金融機関が家族信託に積極的というわけではないため、事前に確認が必要です。
まとめ
家族信託(民事信託)は、信頼できる家族に財産管理を任せる、相続対策の新しい選択肢です。
認知症への備え、不動産の円滑な承継、障がいのある家族の将来の保護など、特定の課題を解決する強力な手段になります。しかし、万人に必要な制度ではなく、従来の遺言や成年後見制度の方が適している場合もあります。
相続マルシェでは、税理士・弁護士・司法書士と提携し、お客様の状況に応じた最適なご提案をいたします。事前のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら↓