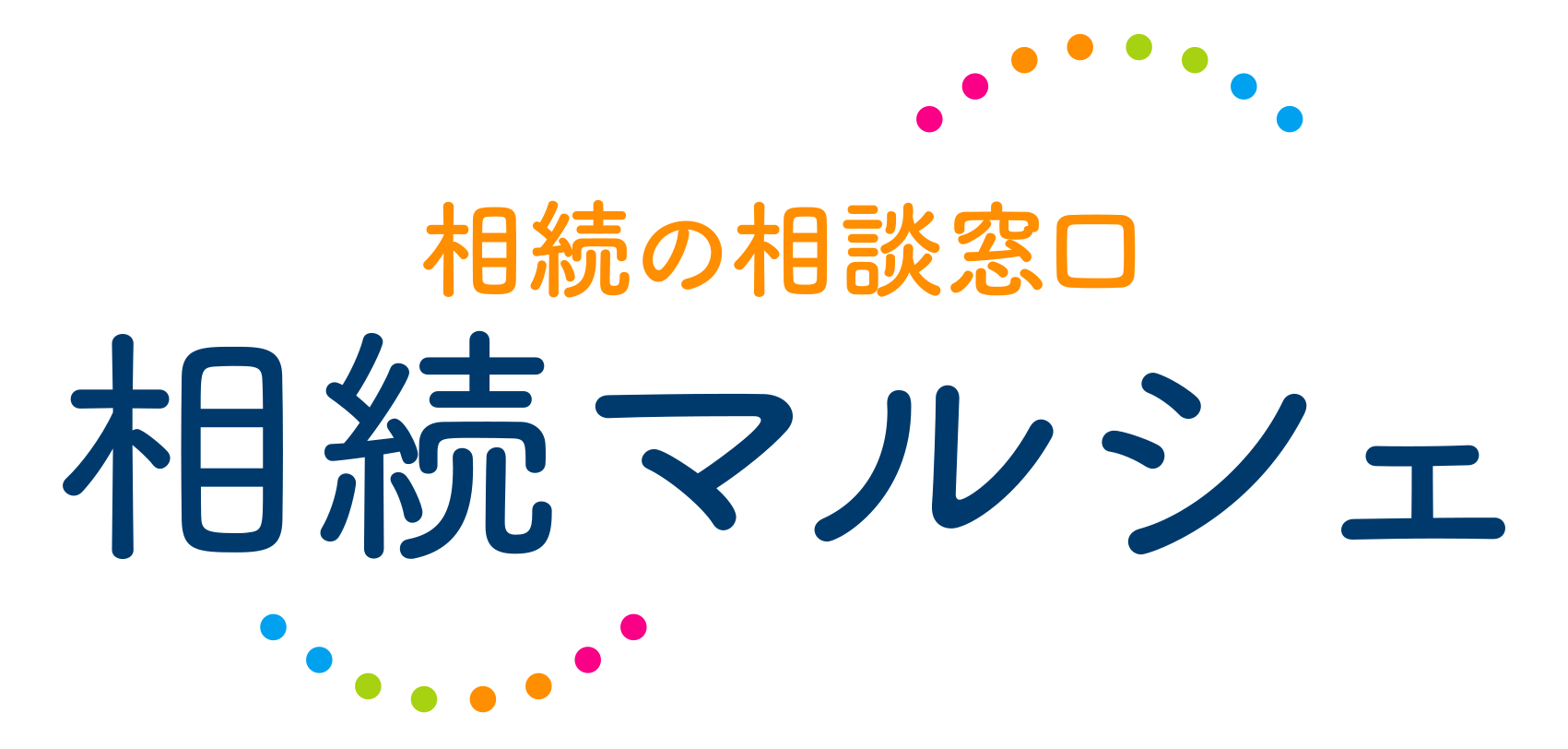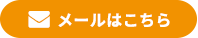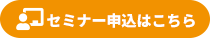ブログ
相続手続きの代行は誰に頼む?弁護士・司法書士・行政書士の違いと選び方
更新日:2025.11.24 コラム
家族が亡くなった後、進めなければならないのが相続手続きです。「何から始めればいいのかわからない」「誰に相談すればいいの?」「弁護士、司法書士、行政書士…どう違うの?」――こうした疑問を抱える方は少なくありません。
相続手続きには、戸籍の収集、財産調査、不動産の名義変更、税務申告など、多岐にわたる作業があります。すべてを自分で行うのは大変ですし、専門的な知識も必要です。そこで頼りになるのが専門家ですが、それぞれに得意分野があり、どの専門家を選ぶかによってサポートしてもらえる範囲も変わってきます。
この記事では、各専門家の特徴や自分に合った依頼先の選び方をわかりやすく解説します。
相続手続きはどんな流れで行う?
まずは、相続手続きの全体像を把握しましょう。相続が発生してから完了するまでには、いくつかのステップがあります。
1. 死亡届の提出と初期手続き(死亡後7日以内)
市区町村役場に死亡届を提出します。この時点では専門家に依頼する必要はなく、ご家族で対応できます。
2. 遺言書の確認
遺言書がある場合は、家庭裁判所で検認手続き(自筆証書遺言の場合)が必要です。公正証書遺言の場合は検認不要です。
3. 相続人の確定(戸籍収集)
亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集め、誰が相続人なのかを確定します。本籍地が複数ある場合、各市区町村から取り寄せる必要があり、時間と手間がかかります。しかし、現在、相続人様が運転免許証やマイナンバーカードを役所に持参することで一度のお手続き(広域交付制度)で、これらの取得ができるようになりました。
4. 相続財産の調査
不動産、預貯金、株式、生命保険、借金など、プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべて調査します。金融機関への照会や不動産の評価など、専門的な知識が必要になることもあります。
5. 相続放棄・限定承認の判断(死亡を知った日から3ヶ月以内)
借金が多い場合などは、相続放棄を検討します。期限があるため、早めの判断が必要です。
6. 遺産分割協議
相続人全員で、誰がどの財産を受け取るかを話し合い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
7. 不動産の名義変更(相続登記)(義務化:相続を知った日から3年以内)
令和6年4月から相続登記が義務化されました。不動産がある場合は、必ず法務局で名義変更の手続きが必要です。
8. 預貯金・証券などの名義変更・解約
各金融機関で必要書類を提出し、手続きを行います。
9. 相続税の申告・納付(死亡を知った日から10ヶ月以内)
相続税がかかる場合は、税務署へ申告し、納税します。
「すべて専門家に任せる」のではなく、「難しい部分だけサポートしてもらう」という考え方も可能です。まずは相談してみて、どこまで自分でやるか、どこから依頼するかを決めると良いでしょう。
弁護士の特徴
弁護士の最大の強みは、相続トラブル・争いの解決です。相続人同士で意見が対立している場合や、遺産分割で揉めている場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士にできること
- 相続人の代理人として、他の相続人と交渉
- 遺産分割調停・審判の代理
- 相続放棄の手続き代理 等
※弁護士は、他士業に存在する「業務範囲の制限」は原則ありません。
そのため、相続に関連する法律事務全般のお手続きが可能です。
司法書士の特徴
司法書士の専門分野は、不動産の名義変更(相続登記)と書類作成です。相続財産に不動産が含まれている場合、司法書士が心強い味方になります。
司法書士にできること
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の取得
- 戸籍謄本などの必要書類の収集代行
- 相続放棄の申立書類作成(裁判所への代理提出はできない)
※司法書士は「書類作成」と「登記手続き」が中心で、相続人間で争いがある場合の代理交渉や調停代理はできません。ここが弁護士との大きな違いです。
令和6年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内に登記しないと過料(罰金)が科される可能性があります。このため、司法書士への相続登記依頼が増加しています。「後回しにしていた」という方も、早めに手続きを進めることをおすすめします。
行政書士の特徴
行政書士は、書類作成と届出のサポートが中心です。比較的シンプルな相続手続きで、費用を抑えたい場合に適しています。
行政書士にできること
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 行政への各種届出書類の作成
- 自動車の名義変更手続き
※行政書士は「書類作成専門職」であり、法的な紛争対応(代理交渉・調停)や登記手続きは行えません。
自分に合った専門家の選び方
「結局、誰に頼めばいいの?」と迷う方も多いと思います。ここでは、目的別の判断基準をご紹介します。
【目的別の判断基準】
相続人間で揉めている、またはトラブルの予兆がある → 弁護士
争いが発生している、または発生しそうな場合は、迷わず弁護士に相談しましょう。代理人として交渉や調停に対応できるのは弁護士だけです。
不動産(自宅)の名義変更が必要 → 司法書士
土地や建物を相続した場合は、司法書士に依頼するのが一般的です。相続登記は義務化されているため、期限内に確実に手続きを完了させることが重要です。
自動車の名義変更が必要 → 行政書士
遺産が預貯金や動産のみで、相続人全員が協力的な場合は、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼するとコストを抑えられます。
相続税の申告が必要 → 税理士
遺産総額が基礎控除額を超える場合は、税理士に相続税の申告を依頼しましょう。税務の専門家として、適切な節税対策も提案してくれます。
ワンストップ対応事務所を利用するメリット
最近では、弁護士・司法書士・税理士が連携した「ワンストップ対応」の事務所も増えています。このようなネットワークを持つ事務所に相談すれば、複数の専門家に個別に依頼する手間が省け、スムーズに手続きが進みます。
例えば、司法書士に相続登記を依頼したら、「相続税の申告は提携している税理士を紹介しますね」というように、必要に応じて適切な専門家につないでもらえます。
また、「どの専門家が必要かわからない」という段階でも、まず一人の専門家に相談すれば、全体を見た上で「この部分は別の専門家が適していますね」とアドバイスをもらえることもあります。
初回相談を活用
多くの専門家が、初回相談を無料または低料金で提供しています。「こんなこと聞いてもいいのかな」と思わず、まずは気軽に相談してみてください。相談することで、全体像が見えてきますし、その専門家の対応や雰囲気も確認できます。
複数の専門家に相談して比較することも、もちろん可能です。信頼できる専門家を見つけることが、スムーズな相続手続きへの第一歩です。
まとめ
相続手続きを依頼できる専門家には、それぞれ得意分野があります。
- 弁護士:相続トラブル・争いの解決、代理交渉
- 司法書士:不動産の名義変更(相続登記)、書類作成
- 行政書士:書類作成、届出のサポート
- 税理士:相続税の申告、税務相談
どの専門家を選ぶかは、あなたの状況や目的によって変わります。相続人間で揉めている場合は弁護士、不動産がある場合は司法書士、書類作成のサポートが欲しい場合は行政書士、というように考えてみてください。 相続マルシェでは、税理士・弁護士・司法書士と提携し、お客様の状況に応じた最適なご提案をいたします。
事前のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら↓