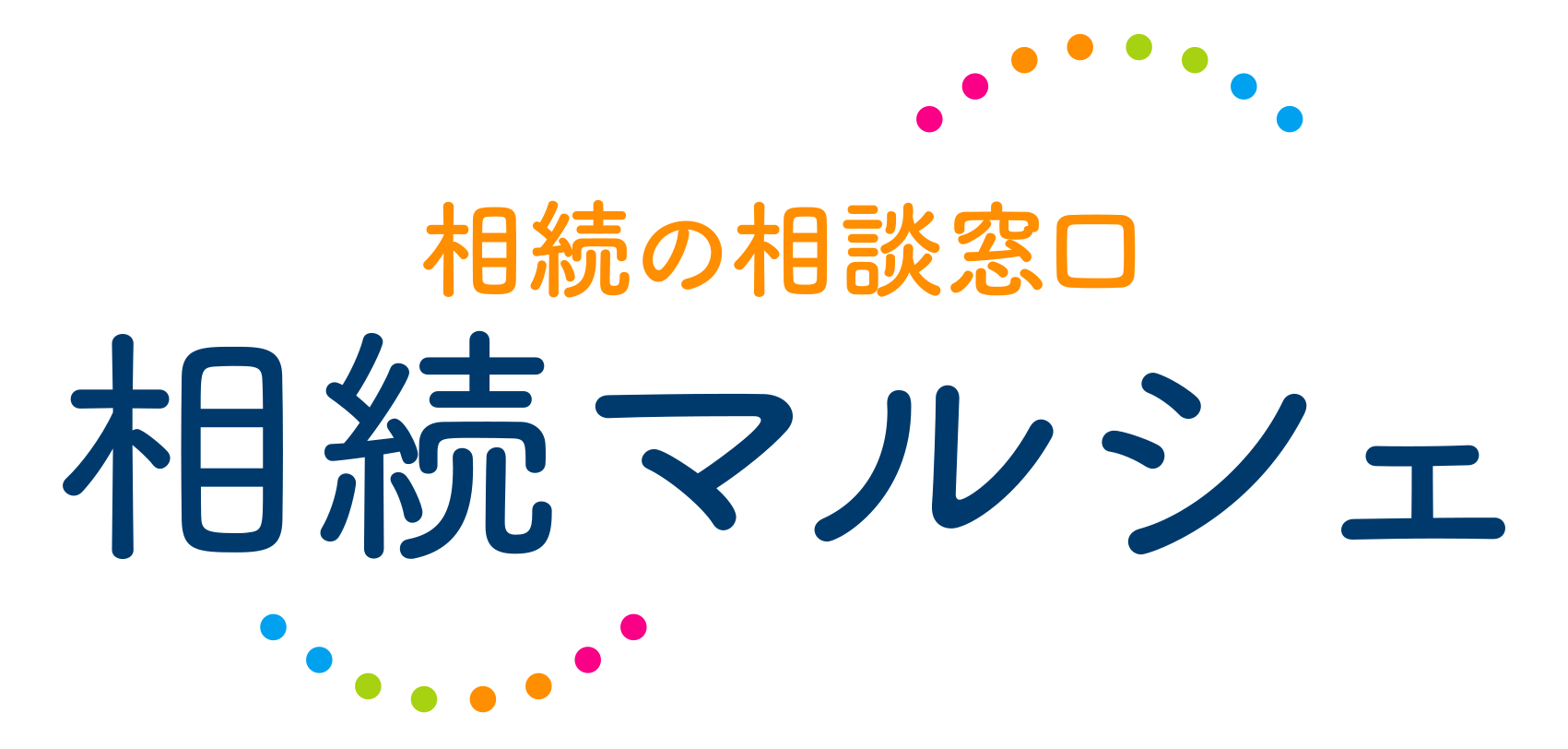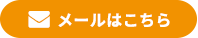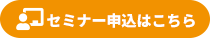ブログ
デジタル財産とは?相続手続きと生前対策について
更新日:2025.10.22 コラム
「亡くなった家族のスマホに何が入っているかわからない」「ネット銀行の口座があるかもしれないけれど、確認する方法が…」現代社会では、こうしたデジタル財産に関する悩みを抱える方が急増しています。
スマートフォンやパソコンの中には、銀行口座やクレジットカード情報、SNSアカウント、サブスクリプションサービスなど、様々な財産や契約が保管されています。しかし、ID・パスワードがわからず、家族が途方に暮れるケースが後を絶ちません。
この記事では、デジタル財産の相続について、何が財産として扱われるのか、どのような手続きが必要か、そして生前にできる対策まで、解説します。
金融資産関連
デジタル財産として最も重要なのが金融資産です
ネット銀行・証券口座
• オンライン専業銀行(楽天銀行、PayPay銀行など)
• ネット証券(楽天証券、SBI証券など)
• 外貨預金口座
電子マネー・キャッシュレス決済
• 交通系IC(Suica、PASMO)
• QRコード決済(PayPay、楽天Pay、d払いなど)
• 電子マネー(nanaco、WAONなど)
仮想通貨(暗号資産)
• ビットコイン、イーサリアムなどの暗号資産
• 取引所のアカウント
• ウォレットの秘密鍵
オンラインサービス・サブスクリプション 有料サービス
• 動画配信(Netflix、Amazon Prime、Disney+など)
• 音楽配信(Spotify、Apple Music、Amazon Musicなど)
• クラウドストレージ(iCloud、Googleドライブ、Dropboxなど)
• オンライン学習、ゲーム課金など
個人情報を含むアカウント
• SNS(Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、LINEなど)
• メール(Gmail、Yahoo!メール、Outlookなど)
• ブログ、noteなどの執筆プラットフォーム
購入済みの電子データ
• 電子書籍(Kindle、楽天Koboなど)
• 音楽、映画のダウンロード購入分
• ゲームのダウンロード版
• 写真、動画データ
相続財産になるもの・ならないもの
相続財産として扱われるもの
法律上、経済的価値があるものは相続財産となります
明確に相続財産となるもの
• ネット銀行の預金
• ネット証券の株式・投資信託
• 仮想通貨
• 電子マネーの残高
• 有料デジタルコンテンツ(ただし利用規約による制限あり)
これらは相続税の計算対象にもなるため、正確な把握が必要です。
相続財産として扱われないもの
一方、人格的な要素が強いものや、規約で譲渡が禁止されているものは相続財産になりません
相続の対象外となるもの
• SNSアカウント(多くの場合、規約で譲渡不可)
• ポイント(規約により相続不可の場合が多い)
• サブスクリプションの契約(契約者本人に紐付く)
• メールアカウント(多くは譲渡不可)
ただし、規約はサービスによって異なるため、個別に確認が必要です。
デジタル財産を放置した場合のリスク
不正アクセス・悪用のリスク
デジタル遺品を放置すると、以下のようなリスクがあります
セキュリティ上の危険
• スマホやPCが第三者の手に渡り、不正アクセスされる
• 金融口座から不正に出金される
• SNSアカウントが乗っ取られ、詐欺に利用される
• クレジットカード情報が悪用される
継続課金
気づかずに放置していると、毎月の課金が続きます
継続課金の例
• 動画配信サービス:月額500円〜2,000円
• 音楽配信サービス:月額980円前後
• クラウドストレージ:月額数百円〜数千円
• オンラインゲーム課金:月額数千円〜数万円
年間で数万円から十数万円の無駄な支出になることもあります。
相続税の申告漏れ
ネット銀行や仮想通貨の存在に気づかず、相続税の申告漏れが発生するリスクもあります。税務調査で発覚すると、追徴課税や加算税が課される可能性があります。
相続人ができる手続きと対応方法
ID・パスワードの確認方法
まずは故人のデジタル情報にアクセスする必要があります
確認すべき場所
• 手帳やノートのメモ
• パソコン内のテキストファイル
• スマホのメモアプリ
• メールの受信履歴(サービス登録時の通知メール)
• 郵便物(紙の通知が届いているサービス)
故人がパスワード管理アプリを使用していた場合、マスターパスワードがあればすべてのアカウント情報にアクセスできます。
サービスごとの解約・相続手続き
金融機関の場合
1. カスタマーサポートに連絡
2. 死亡診断書や戸籍謄本などの必要書類を提出
3. 相続人全員の合意書類を提出
4. 残高の払い戻しまたは相続手続き
サブスクリプションサービスの場合
1. サービスのサポートに連絡
2. 契約者の死亡を伝える
3. 解約手続きを依頼
4. 日割り返金の有無を確認
SNSアカウントの場合
• Facebook:追悼アカウント化または削除
• Instagram:追悼アカウント化または削除
• LINE:削除(相続不可)
• X(旧Twitter):削除申請(家族が代理で可能)
各サービスには「故人のアカウント」に関する専用の問い合わせフォームが用意されていることが多いです。
仮想通貨の相続手続き
仮想通貨は特に注意が必要です
取引所に預けている場合 取引所のカスタマーサポートに連絡し、相続手続きを行います。本人確認書類や相続関係書類が必要です。
個人のウォレットで管理している場合 秘密鍵(シークレットフレーズ)がわからないと、永久にアクセスできなくなります。復元フレーズを見つけることが最優先です。
生前にできる対策
エンディングノートの活用
デジタル財産対策として、エンディングノートは非常に有効です
記載すべき情報
• 主要なアカウントの一覧(サービス名、登録メールアドレス)
• 金融機関の情報(銀行名、支店、口座番号)
• 重要なID・パスワード(厳重に保管)
• 仮想通貨の保管場所と復元フレーズ
• 解約してほしいサービス、残してほしいデータ
ただし、パスワードを直接書くのはセキュリティ上リスクがあるため、ヒントを書くなど工夫が必要です。
パスワード管理サービスの利用
家族と共有できる管理方法
• 信頼できるパスワード管理アプリを使用
• 緊急連絡先機能を設定(1Password、LastPassなど)
• 家族がマスターパスワードを知っている状態にする
デジタル終活サービスの活用
最近では、デジタル遺品専門のサービスも登場しています
利用できるサービス例
• デジタル遺品整理業者
• オンラインアカウント管理代行サービス
• 死後の自動メッセージ送信サービス
家族との情報共有
定期的なコミュニケーション
• どのようなサービスを利用しているか家族に伝える
• 重要な情報の保管場所を共有
• 年に一度は情報を更新
まとめ
デジタル財産は、従来の相続とは異なる複雑さがあります。ID・パスワードがわからなければアクセスできず、放置すれば経済的損失やセキュリティリスクにつながります。
重要なポイント
• デジタル財産には金融資産からSNSまで幅広い範囲が含まれる
• 相続財産になるものとならないものを区別する
• 放置すると継続課金や不正アクセスのリスクがある
• 生前にエンディングノートやパスワード管理で準備できる
デジタル財産の問題は、今後ますます重要になっていきます。「まだ早い」と考えず、今から少しずつ準備を始めることが大切です。
家族が困らないように、そして大切な財産を確実に引き継ぐために、デジタル時代の相続準備を今日から始めましょう。
相続マルシェでは、税理士・弁護士・司法書士と提携し、お客様の状況に応じた最適なご提案をいたします。事前のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら↓