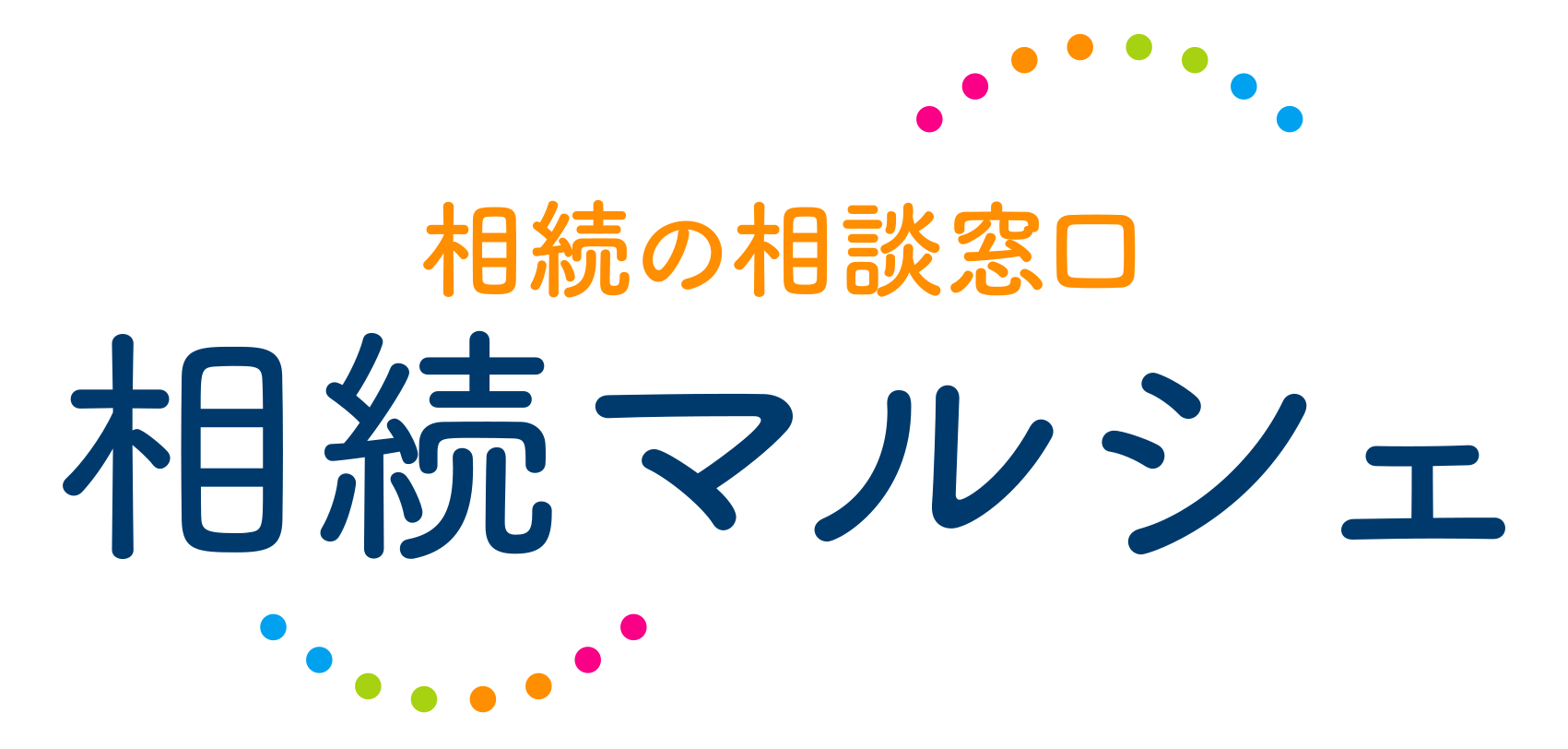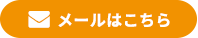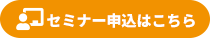ブログ
不動産の相続手続きとは?登記・税金・遺産分割の流れと注意点を解説
更新日:2025.09.26 コラム
「親が亡くなって実家を相続することになったけれど、何から手をつければいいの?」「相続登記って義務化されたって聞いたけど、どんな手続きが必要?」
不動産の相続は、預貯金の相続とは異なり複雑な手続きが必要で、多くの方が戸惑いを感じる分野です。
不動産は「分割しにくい財産」という特徴があり、相続人同士で意見が分かれやすく、手続きも登記・税務・法律など多岐にわたります。また、2024年4月から相続登記が義務化されたため、適切なタイミングでの手続きがより重要になりました。
この記事では、不動産の相続手続きの基本的な流れから注意すべきポイントまで、わかりやすく詳しく解説します。正しい知識を身につけて、安心して手続きを進めましょう。
不動産は相続財産に含まれる
土地・建物は現金とは違い「分割しづらい財産」
不動産の相続において最も重要な特徴は、土地や建物が現金のように簡単に分割できない財産だということです。預貯金であれば相続人の人数に応じて分割できますが、不動産は物理的に分割することが困難で、価値の評価も複雑です。
例えば、3,000万円相当の自宅を3人の相続人で相続する場合、現金なら1,000万円ずつ分けられますが、不動産では
一人が不動産を取得し、他の相続人に金銭を支払う「代償分割」
不動産を売却して現金で分ける「換価分割」
複数人で共有する「共有分割(現物分割)」
といった方法から選択する必要があります。
所有者が死亡すると、法定相続人に相続権が発生
不動産の所有者が亡くなると、自動的に法定相続人全員の共有財産となります。つまり、手続きをしなくても法的には相続人全員が不動産の権利を持つことになります。
ただし、この状態では不動産の売却や担保設定ができず、管理責任も曖昧になるため、速やかに名義変更(相続登記)を行う必要があります。
相続の基本的な流れ(不動産ありの場合)
相続人の確定
まず、誰が相続人になるかを確定します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を正確に把握します。相続人の範囲を間違えると、後の手続きすべてに影響するため、この段階での正確性が重要です。
遺産分割協議
相続人が確定したら、遺産分割協議を行います。不動産をどのように分割するか、誰が取得するかを相続人全員で決定し、合意内容を遺産分割協議書に記載します。
相続登記の申請
遺産分割協議が成立したら、法務局で相続登記の申請を行います。相続登記義務化により、この手続きは法的義務となっており、期限内に完了させる必要があります。
相続税の申告と納付(必要な場合)
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続開始から10ヶ月以内に43相続税の申告・納付が必要です。不動産は高額になることが多いため、相続税の対象となるケースも少なくありません。
相続登記の義務化について
相続登記の概要と義務化の背景
相続登記とは、亡くなった方から相続人への不動産の名義変更手続きです。2024年4月1日から相続登記の義務化が施行され、これまで任意だった手続きが法的義務となりました。
義務化の背景には、所有者不明土地問題の深刻化があります。全国で約410万ヘクタールの所有者不明土地が存在し、公共事業の妨げや災害復旧の障害となっていることから、この制度が導入されました。
3年以内の申請義務と罰則(10万円以下の過料)
相続を知った日から3年以内に申請することが義務付けられています。正当な理由なくこの期限を守らない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続についても、2027年4月1日までに登記申請を行う必要があります。
名義変更を怠るリスク
相続登記を怠ることで生じるリスクは過料だけではありません。不動産の売却ができない、金融機関からの融資を受けられない、次の相続でさらに複雑化するなど、様々な問題が発生する可能性があります。
不動産の遺産分割における注意点
共有にすると将来トラブルになりやすい
不動産の共有は法的には可能ですが、実務上は多くの問題を引き起こします。共有者全員の同意がないと売却できない、管理方針で意見が分かれる、次の相続でさらに共有者が増えるなど、トラブルの原因となることが多いです。
可能な限り、代償分割や換価分割により単独所有にすることをお勧めします。
協議がまとまらないと登記・税務手続きに支障
遺産分割協議がまとまらないと、相続登記ができず、義務化による過料のリスクが生じます。また、相続税の申告期限(10ヶ月以内)にも影響し、様々な特例制度の適用ができなくなる可能性があります。
「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」が使えない場合もある
相続税の軽減制度の多くは、相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していることが適用要件となっています。
小規模宅地等の特例では、居住用宅地について330㎡まで80%の評価減が可能ですが、申告期限までに協議が成立していない場合は適用できません。配偶者の税額軽減についても同様で、協議の遅れが大幅な増税につながる可能性があります。
相続税のポイント(不動産の評価と控除)
路線価・固定資産税評価額
不動産相続税の計算では、土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基準として評価されます。これらの評価額は一般的に時価よりも低く設定されているため、不動産による相続は現金による相続よりも税務上有利になることが多いです。
小規模宅地等の特例
被相続人の居住用や事業用の宅地について、大幅な評価減を受けられる制度です
- 居住用宅地:330㎡まで80%減額
- 事業用宅地:400㎡まで80%減額
- 貸付事業用宅地:200㎡まで50%減額
この特例により、数千万円の節税効果を得られる場合があります。
配偶者控除・基礎控除の活用
配偶者は1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。また、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)により、多くのケースで相続税の負担を軽減できます。
よくあるトラブルと対応策
相続人間の意見不一致
不動産の価値評価や分割方法について相続人間で意見が分かれることがあります。このような場合は、複数の専門家による評価を取得し、客観的な数値に基づいて話し合いを進めることが重要です。
売却 or 相続して賃貸に出すなどの選択肢
不動産を相続した後の活用方法について、売却、賃貸、自己使用など様々な選択肢があります。それぞれの税務上の取り扱いや将来的な資産価値を考慮して判断する必要があります。
遺言書がない場合の対応
遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要です。話し合いが円滑に進むよう、早い段階から相続人同士でコミュニケーションを取ることが大切です。
まとめ
不動産の相続は、登記の義務化、複雑な税制、分割の困難さなど、多くの課題を含む手続きです。しかし、適切な知識と早めの準備により、これらの課題を解決し、円滑な相続を実現することができます。
不動産相続は複雑だからこそ、早めの準備と専門家への相談が重要です。一人で悩まず、信頼できる専門家とともに、安心できる相続手続きを進めていきましょう。
相続マルシェでは、税理士・弁護士・司法書士と提携し、お客様の状況に応じた最適なご提案をいたします。事前のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら↓