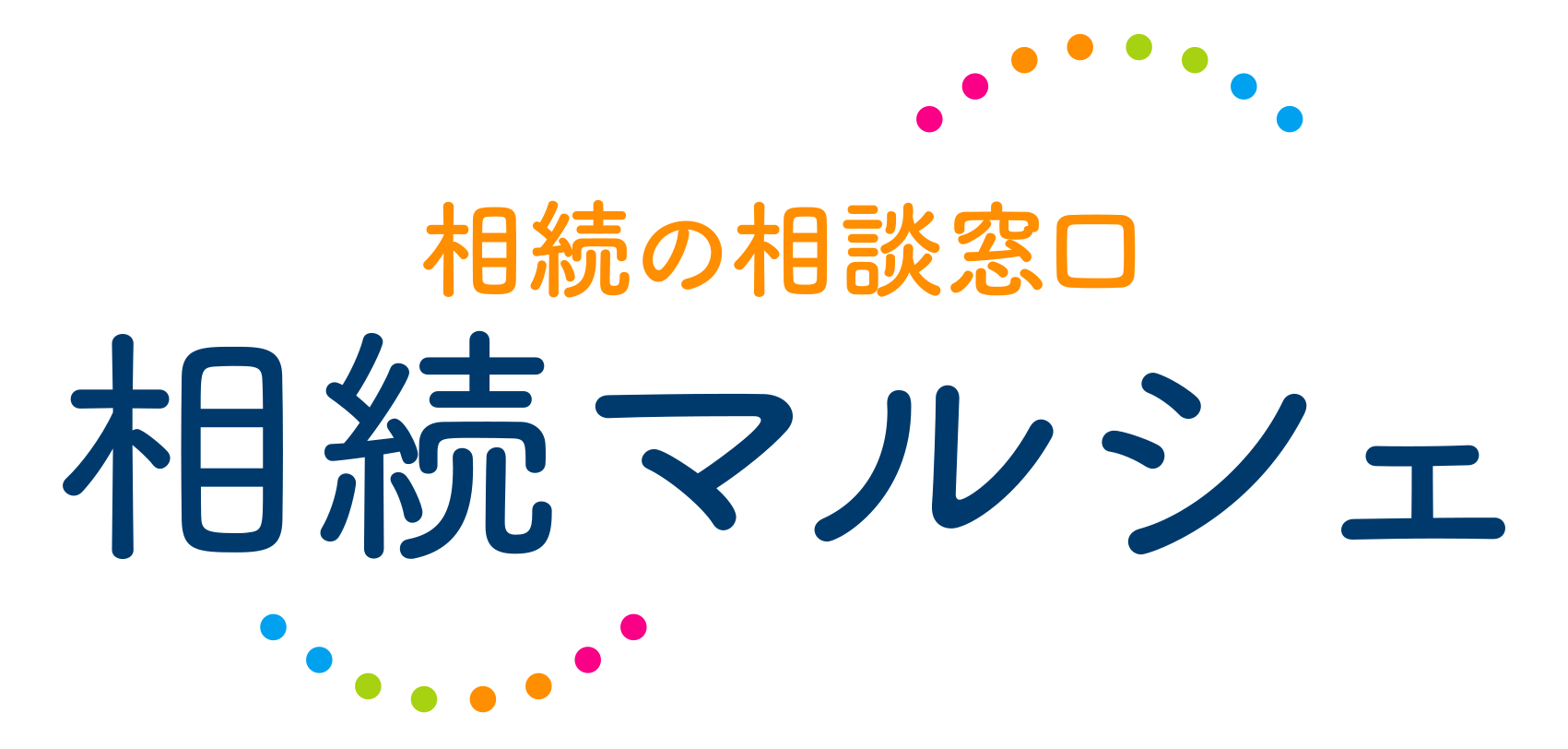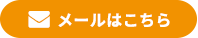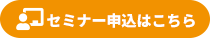ブログ
ペットに相続はできる?「遺言」や「ペットのための信託」の仕組みと準備のポイント
更新日:2025.08.22 コラム
「もし自分に何かあったら、この子はどうなるんだろう…」
愛するペットと暮らしている方なら、一度はそんな不安を感じたことがあるのではないでしょうか。特に一人暮らしの方や子どもがいない方にとって、ペットは家族同然の存在です。
この記事では、ペットを取り巻く法律の現実から具体的な対策方法まで、わかりやすく解説します。
ペットに「相続」はできるのか?
法律上ペットは「財産」として扱われる
残念ながら、法律上では「動産」つまり財産として扱われており、ペット自身が相続人になることはできません。現在の日本の法制度では、権利義務の主体となれるのは人間と法人のみとされています。
つまり、「愛犬に全財産を相続させる」という遺言書を作成しても、法的には効力を持たないということになります。
ペット自身にお金や財産を渡すことはできない
ペット自身に直接財産を渡すことは法律上不可能です。しかし、これは決してペットを守る方法がないということではありません。
法律的な制約がある中でも、飼い主の想いを実現し、ペットの幸せな生活を確保する方法は複数存在します。重要なのは、正しい知識と適切な手続きにより、実効性のある対策を講じることです。
ペットを守るための方法
1、相続制度を使った対策
・遺言書で飼育を託す
最も一般的な方法は、遺言書の中で信頼できる人に飼育を託すことです。この際、以下の内容を明確に記載することが大切です
- ペットを引き取ってもらう人の指定
- ペットの飼育費用として一定額の遺贈
- ペットの好き嫌いや病歴などの詳細情報
- 飼育方法に関する具体的な希望
ただし、遺言書は不完全な制度で、無効になるリスクもあり、かつ指定した人が必ずしもペットを引き取ってくれるとは限らず、法的強制力には限界があります。
・負担付き遺贈の活用
より確実性を高める方法として、負担付き遺贈があります。これは「財産を遺贈する代わりに、一定の義務を負ってもらう」という仕組みです。
具体的な内容例
- 「Aさんに500万円を遺贈する。ただし、愛犬が天寿を全うするまで適切に飼育すること」
- 「Bさんに自宅不動産を遺贈する。ただし、愛猫たちの世話を責任持って行うこと」
負担付き遺贈のメリット
- 財産と義務をセットにすることで、より確実な飼育の確保が期待できる
- 遺贈を受ける人にとってもメリットがあるため、協力を得やすい
- 法的な強制力が一定程度期待できる
注意点
- あくまでも受遺者の「気持ち次第」となり、法的不安定性は変わらない
- 受遺者が負担を履行しない場合の対応策を検討しておく必要がある
2、未来信託を使った対策
・「ペットのための信託」の仕組み
さらに別の方法として「ペットのための信託」があります。これは信託法を活用した仕組みで、以下のような構造になっています
信託の基本構造
- 委託者兼最初の受益者:ペットの飼い主(信託を設定する人)
- 受託者:信託財産を管理し、ペットの世話をする施設などに支払いをする人
- 次の受益者:「ペットの世話代」を除く、他の財産を承継する人
※受益者が保有する「受益権」は、民法上の相続とは関係なく、信託契約のみでもって承継される(ただし、相続税については「みなし相続」として課税される)。
この仕組みにより、ペット自身が直接財産を相続することはできなくても、ペットのための財産管理と適切な飼育を法的に確保できます。
つまり、飼い主の死亡後にも、実質的にペットに財産を所有させているのと同じような状況を作り出すことができるようになるのです。
受託者・飼育担当者、信託監督人などの指定
「ペットのための信託」は、以下の役割を明確に分けることで実効性がアップします。
信託の受託者
信託財産の管理と飼育費用の支払いを行う人です。信頼できる第三者(親族や関係会社など)を指定することで、適切な財産管理体制を確保できます。
飼育担当者(世話人)
実際にペットの日常的な世話をする人です。家族、友人、ペット関連事業者などが候補となります。
信託監督人
受託者の仕事や、施設におけるペットの飼育状況などを見守り、適切なアドバイスを行う人です。ペットの性質を理解しており、信頼できる第三者(ペット関係の専門家など)を指定します。
この役割分担により、「ペットの世話は得意だが財産管理は不安」「財産管理はできるが実際の飼育は難しい」「適切な飼育施設を選定したい」といった場合にも柔軟に対応できます。
まとめ
ペットへの相続は法律上直接的には不可能ですが、遺言書の活用や「ペットのための信託」の設定により、愛するペットの将来を確実に守ることができます。
重要なポイントは、早めの準備と適切な専門知識の活用です。ペットの年齢や健康状態、飼い主の家族構成や財産状況などを総合的に考慮して、最適な方法を選択することが大切です。
今できること
- ペットを引き取ってくれる可能性のある人との事前相談
- 必要な費用の概算と財産の準備
- 専門家への相談と具体的な手続きの検討
- ペットの詳細情報(好き嫌い、病歴、性格など)の整理
愛するペットとの幸せな時間を大切にしながら、同時に将来への備えも進めていきましょう。適切な準備により、ペットの幸せな生活を継続的に守ることができます。
相続マルシェでは、税理士・弁護士・司法書士と提携し、お客様の状況に応じた最適なご提案をいたします。事前のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら↓