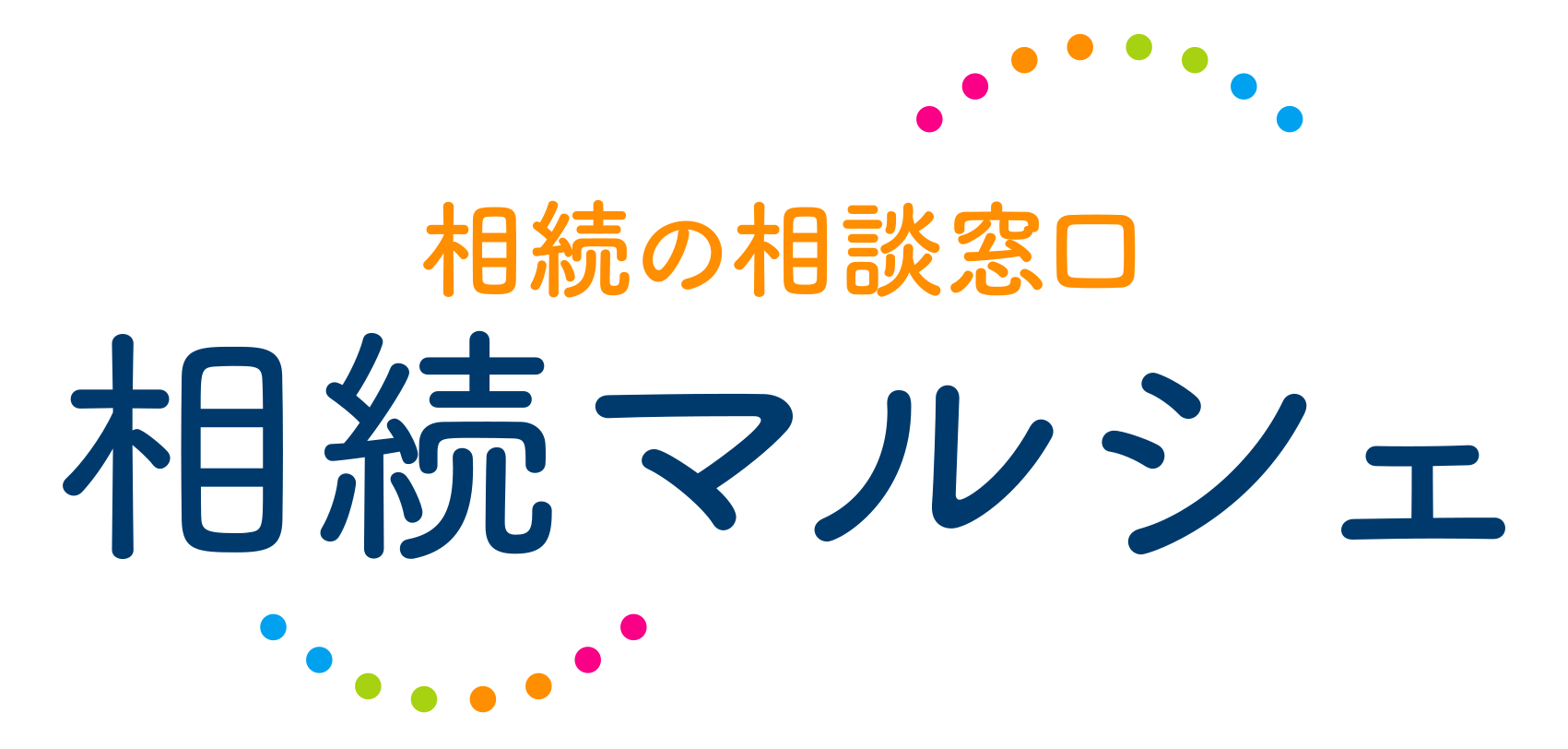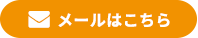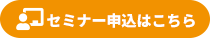ブログ
子どもがいない時の相続|夫婦間と独身それぞれのケースを解説
更新日:2025.08.15 コラム
子どもがいない夫婦や、独身の場合誰が相続人になるのかと不安や疑問をお持ちの方は少なくありません。一般的な相続とは大きく異なる特徴があるため、思わぬトラブルに発展することがあります。
子どもがいないケースでは相続人の範囲が複雑になりやすく、遺産分割協議が難航したり、不動産が共有状態になって管理が困難になったりするリスクがあります。
この記事では、子どものいない夫婦の相続と独身の相続それぞれのパターンについて、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
子どもがいない相続の基本ルール
法定相続人の順位
子どもがいない相続では、以下の順位で相続人が決まります
第1順位:親(直系尊属) 被相続人の父母が相続人となります。
第2順位:兄弟姉妹 親も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。
配偶者の相続割合
配偶者は常に相続人となり、他の相続人と一緒に相続します
- 配偶者と親:配偶者2/3、親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
夫婦間に子どもがいない場合
親が生きているケース
夫または妻が亡くなった場合、相続人の範囲は配偶者と被相続人の親になります。
具体例: 夫が亡くなり、妻と夫の両親が健在の場合、相続分は妻が2/3、夫の両親が1/3となります。夫の両親が2人とも健在なら、それぞれが1/6ずつの相続権を持ちます。
この場合、義理の親との遺産分割協議が必要となり、関係性によってはスムーズに進まない可能性があります。
親が亡くなり兄弟姉妹が相続人になるケース
被相続人の親が既に亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。
具体例: 夫が亡くなり、夫の両親は既に他界、夫に兄弟2人がいる場合、相続分は妻が3/4、夫の兄弟がそれぞれ1/8ずつとなります。
独身で子どもがいない場合
親が相続人になるケース
独身の相続で親が健在の場合、両親が相続人となります。父母が2人とも健在なら、それぞれが1/2ずつ相続します。
親が亡くなり兄弟姉妹が相続人になるケース
親が既に亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分割されます。
具体例: 独身の方が亡くなり、兄弟3人がいる場合、それぞれが1/3ずつ相続します。
甥・姪が相続するケース
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子である甥・姪が代襲相続します。この場合、相続人の数が多くなり、遺産分割協議がより複雑になります。
生前にできるトラブル対策
遺言書の作成
子どもがいない相続への対策として、遺言書の作成が考えられます。遺言書がある場合はその内容が優先されるため、配偶者に全財産を相続させたい場合や、特定の相続人に多く財産を残したい場合、遺言書により自分の意思を明確に示すことができます。公正証書遺言を作成することで、より確実性の高い遺言書を残せますが、後の遺言が優先されてしまうので、法的には不安定性が残ってしまいます。
また、遺言では「次の次」の財産承継者までは指定できず、配偶者に相続された財産は、その次は配偶者側の親族に渡ってしまい、当初の遺言者側には戻ってこないという弱点や、根本的な問題として、遺言から外された一部の相続人から「遺留分侵害額請求」をされると必ず金銭を渡さなければならないという弱点があります。
生前贈与の活用
相続時の負担を軽減するため、生前贈与を活用する方法があります。年110万円の基礎控除を活用した暦年贈与や、相続時精算課税制度を利用することで、計画的に財産を移転できます。配偶者への居住用不動産の贈与特例なども検討する価値があります。
ただし、生前贈与をしても、「持戻し制度」というものがあり、遺留分侵害額請求の対象にされてしまうという弱点があります。
未来信託の検討
未来信託は、民法ではなく信託法に基づいて財産が承継されるので、「相続」や「後見」とは無関係に、財産の管理・承継について柔軟な仕組みを構築できる制度です。一般的には信託契約を締結しますので、遺言よりも遥かに法的安定性が高くなりますし、子どもがいない相続において、一度は配偶者に渡した財産(受益権)を、配偶者死亡後は自分の親族側に戻すという、相続の世界では絶対に不可能な「受益者連続」という仕組みが活用できます。(相続税に関しては「みなし相続税」が課されます)
また、親や配偶者などの認知症対策である「家族信託」を包含しており、共有名義になった不動産や分散した株式の「名義」のみを信頼できる人に委託することで、課税されることなく名義を一本化するなどの効果もあります。
専門家による総合的なサポート
これらの対策は単独で行うよりも、税理士、弁護士、司法書士などの専門家チームによる総合的なサポートを受けることで、より効果的なスキームを構築できます。
個々の状況に応じた最適な組み合わせを提案してもらうことが重要です。
まとめ
子どもがいない相続は、相続人の範囲が複雑になりやすく、思わぬトラブルに発展するリスクがあります。子なし夫婦の相続では配偶者以外に義理の親や兄弟姉妹が関わり、独身の相続では兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる可能性があります。
子どもがいない相続は、一般的な相続よりも複雑な側面があるため、専門家に相談して最適な対策を検討することをお勧めします。
相続マルシェでは、税理士・弁護士・司法書士と提携し、お客様の状況に応じた最適なご提案をいたします。
事前のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら↓